おかず書評⑮【仕事なんか生きがいにするな】
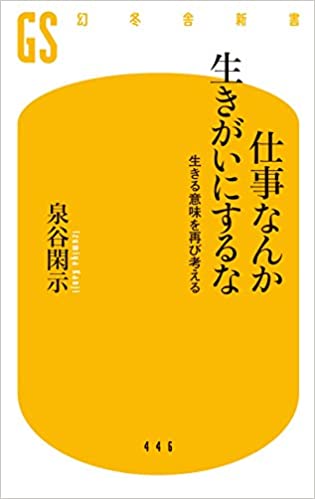
【はじめに】
僕は、今の仕事に就いてもうすぐ丸17年。
1日の殆どの時間を仕事に費やし、新しいことにチャレンジしながら全力疾走を
続けてきたんだけど、こんな仕事漬けで良いんだろうか?
って疑問を最近特に感じてる。
もちろん仕事によって得るものは大きいし、やりがいもある。
だけど、人生も折り返しに近づく中で、もっと違う生き方もあったのかな?って。
いわゆる意味迷子ってわけじゃないけど、他者の考え方に触れながら自分のことも
振り返ってみたいなと思い、本書を手に取ってみました!
【こんな悩みや課題に効果的】
・仕事にやりがいを感じられない
・毎日時間がただ過ぎて、充実感を得られない
・やりたいことが見つからない
こんな感覚に心当たりがあって、何とかしたいと思ってる方にピッタリ!
【僕がこの本の帯キャッチを書くなら!!】
働くことが目的化している現代。
コロナによって暴かれた虚無の世界から目を覚まし、
自分らしさ、人間らしさを取り戻そう!!
【あらすじ、本の構成】
人生100年時代と言われる現代。
70歳まで『働かなきゃいけない』とほとんどの人が感じていることでしょう。
そうでなくとも、人生の3分の1は仕事時間に費やすわけだし、実りあるものに
したいと考えている人がほとんどだと思います。
では、何のために働くのか?
稼ぐため?食べるため?社会貢献?自己成長?
色んな理由があると思いますが、働く目的を問い直してみる必要があります。
本書は、仕事と労働の違いや、現代人が抱く仕事への違和感などを明らかにし、
どうすれば『自分らしさ』や『人間らしさ』を得られるか?
という問題を紐解いて、そのヒントを与えてくれます!
はじめに
1.生きる意味を見失った現代人
2.現代の高等遊民は何と戦っているのか
3.本当の自分を求めること
4.どこに向かえばいいのか
5.生きることを味わうために
おわりに
このような章立て。
現代人は、『生きる意味や働く意味を見いだせない』という深刻な悩みを抱えている。
また、自分探しとかやりたいことを探しも同様で、若い人を筆頭に答えが出ないまま
何かしらの仕事に時間を投じている。
かつては、『働かざるもの食うべからず』という言葉に代表されるように、社会貢献
していることが当たり前で、そうでない人は価値がないと考えられていた。
その背景には
・産業革命以降、一気に広まった資本主義
・高度成長期のハングリーモチベーション
・他人の価値観の中にしか正解が存在しなかった
・敷かれたレールを歩き、自我を摘まれて生きてきた
上記のように、古い昔からの社会変容の中に要因があることを丁寧に説明しています。
自分や社会に永続的な価値を生み出すはずの仕事が、ただ賃金を得る為だけの労働に
なってしまっていることが、働くことに意味を見いだせない要因だということですね。
その結果、本当の自分探しが仕事探しにすり替わってしまっている。
真の自己は自分の内ではなく外にあり、すでに社会にある職業に就くことで見つかる
という錯覚に繋がっているわけです。
そんな簡単な話じゃないですよね。
本当の自分に出会うためには、まずは労働からの脱出が必要。
労働を仕事に近づけていくことが、人が人らしく生きることに繋がるという事です。
働くことを目的とせず、その中から感情を動かすもの、自分が楽しめることを見つけ
て、使う時間に意味を与えていこうという考え方です。
仕事に限らず、充実させるための手段は沢山あります。
5章では、人らしく生きるということは『遊ぶ』ことだとして、その方法をいくつか
の事例を挙げて紹介しています。
一部を抜粋して紹介すると
〇予定調和からの脱却
何も変わらない毎日も、常に何か違うことが起こる毎日も、自分で選べる。
結果の決まりきった行動ではなく、何も決めずに動いてみる事で、その時
その場でしか発生しない事に出会える。
〇食事を義務にしない
生きる上で呼吸と同じ性質のある食事。
ただのルーティンではなく、食べたいものを味わい、時には手間暇かけて
自分で作ってみると、食事に対して向き合い方が変わる。
〇楽器(趣味)を始めてみる
若いころにやっていた楽器を大人になってからやってみる
下手でもなんでも構わない。資格を求めたりプロを目指すわけでないなら
自分自身で試行錯誤しながら勘所を掴んでいく事が、面白い経験になる。
人は本来、知的探求心を持っています。子どもなんてその塊ですよね!
好奇心と創意工夫でただ遊ぶ。ひらすら何かと戯れる。
そこから、無味無臭な日常に彩が出て、人生に深みを与えるサイクルが生まれます。
効率的なことよりも、面倒と思う事の方が色んな経験に繋がるし、手間暇をかけて
考えたことの方が自分の血肉になりますよね!
そういう意味ではブログも同じかも♪
【一番刺さったのはココ!】
アリとキリギリス
童話ですが、このお話には日本特有の考え方が詰まっています。
苦しいこと・勤勉なことが美徳とされる風習。
今を楽しむことを犠牲にして将来のために貯め込むことがさも善しとされ、
楽しむことは良くないという価値観が今まではあった。
苦しむこと、我慢することこそが正当
楽しむこと、心地よいことは堕落として罪悪感を覚えるという感覚
でもこれ、生き物としてもともと備わっている快・不快という感覚に逆らって、
いちいち逆にして捉えることが、奇妙で滑稽な状態。
働くことをそう捉えれば受け身にもなるし、ただの労働にしか感じられなくなる。
働く意味に疑問を感じる理由の一端がここに詰まってると感じました。
【まとめ】
『パーパス』とか『ワークライフバランス』、『バーンアウト』なんて言葉は以前
は聞かなかったけど、社会的にも働く意味が見直されてきた現代。
二年前に始まったコロナ禍によって、今まで仕事に全振りで走ってきた社会人たちが
強制的に立ち止まることを余儀なくされ、一斉に疑問を持ち始めた。
『何のためにこんな頑張って働いてたんだろ?』
みんなが振り返ってそう思ったという通説はもはや一般論ですね。
でも、そう感じたという事を無視してはいけません。
何故なら、ただの労働に近い状態になっていた可能性があるから。
自分の向き合い方ひとつで、『賃金を得るための労働』から
『自分を見つけ、人間らしく生きるための仕事』に変えることが出来ます。
僕の場合は、前述のように学びややりがいも感じていたけど、食うためだけの労働じゃ
なかったなってことも分かりました。
ただ、どちらかと言えば効率性を重視して、面倒なことを避ける傾向はありました(笑)
料理をする気にはならないけど、心の動くことに時間をもっと使ってみます!
本書の中では、『美と芸術にこそ真理がある』という考えも出てきますが、僕には全く
理解できませんでした。。
あと、歴史的背景や哲学者の言葉なんかをとうとうと語って、現代人の悩みの発生源を
明らかにした後の解決策が『遊ぶ』というギャップも顎落ちでしたねw
読んで考えるうちに、行きつくところが『遊びから人間らしい心の動きを取り戻す』と
いう意味だと解釈し、最終的には腹落ちしました♪
僕の読んできた本の中ではけっこう難しい部類の本でしたが、漠然と悩んでいるような
状態であれば一度読んでみるといろいろスッキリすると思います!
【あとがき】
本書には、哲学者や夏目漱石の小説などから引用した言葉が多々出てきます。
また、著者の言葉も非常に難しい表現を使っています。
例えば、働く人の対義語として『高等遊民』という言葉が出て来ます。
いわゆるニートのことですね。
他にも、熟語表現が多くて意味が分からなかったり、一文が非常に長くオーディオ
ブックだと最初に言ってたことが分からなくなっちゃうぐらいの回りくどさw
でも一つ気付いたのは、自分の読解力のなさ。
こういう文体に全くなじみがないからか、全然頭に入ってこなくて苦労しました。。
逆に、愛と欲望の違い、意味と意義の違いなどの哲学的引用はスッと入ってきた。
ただの、興味の有無だったのかもしれませんねw
とにかく、自分のレベルじゃこういう言葉は読み解けないんだなってことに気付けた
というお話。読み慣れるようにまた色々手を出していきたいと思います♪
それではまた来週お会いしましょう^^
【著者について】
著者:五百田 達成
経歴:作家・心理カウンセラー。株式会社 五百田達成事務所代表。
コミュニケーション×心理」を軸に恋愛や結婚、ジェンダーや言葉
について執筆。累計販売部数100万部近く。
著書:超雑談力
話し方で 損する人 得する人
察しない男 説明しない女 男に通じる話し方 女に伝わる話し方
「言い返す」技術 他多数

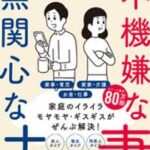
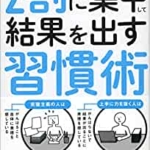
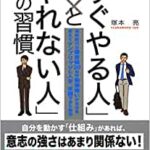
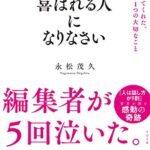
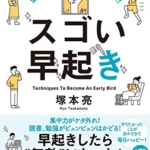
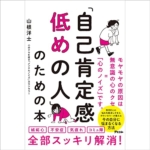
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません